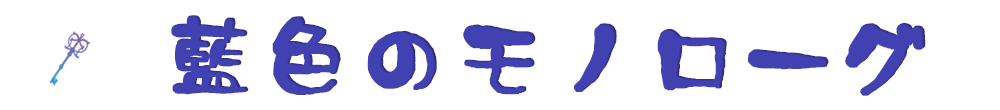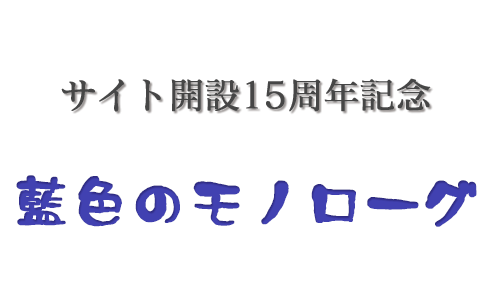技使いとは難儀な生き物だ
技使いというのは難儀な生き物だ。
おおよそとはいえ、『気』で相手の感情がわかってしまう。
それを理由に家に引きこもってしまう子どももいるが、そんなことをしても音のように遮断されるわけでもない。読み取ろうとしなくても、勝手に飛び込んでくる。気から逃れられる術はない。
技使いとは難儀な生き物だ。
川辺にいる見知った姿を目にして、バッキオは立ち止まった。風に揺れる髪を手で押さえ、長いスカートをはためかせながら歩いているのは、間違いなくリンだ。最近忙しかったようでこの辺りではまったく見かけていなかった。声を掛けようか迷った彼は、伸ばしかけた手の先を見つめる。
彼が話しかけると、彼女は必ず一瞬だけ眉根を寄せる。その後すぐに表情は繕われるのだが、その時に感じた気が、彼女の感情を如実に表していた。
嫌われているという一言で済まされるような、簡単なものではない。もっと複雑な色を孕んでいる。温かいとも、冷たいとも言い切れない気。ただ歓迎されていないことだけは間違いなかった。
そういった反応になる心当たりはありすぎるほどにあったので、文句も言えない。もう十年以上にわたって、彼らは口喧嘩を繰り返してきた。喧嘩を売るのはいつも彼の方だ。それをいつも彼女は煙たがっていた。
彼女という存在を意識したのはいつのことだっただろうか? たぶん、出会ったその日からだ。
彼が技使いであると発覚したのは早かったが、近くにある技使いグループに所属したのは遅かった。グループに入るということは、年上の技使いに自由を奪われるも同然だと、ずっと彼は思っていた。
それでも技使い同士でないと思い切って遊ぶこともできない。自由を求めた結果の不自由に耐えかねた彼がグループに顔を出したとき、彼女は既にその中でも目立つ存在だった。
最初に使ったのが、空を飛ぶ技だった。彼女の実力を象徴する事実は、当時七歳だった彼にとっても衝撃だった。しかも新参者だからという理由で呼び捨てにしてきた小さな少女。まだ何もわからない幼子なのだと周りに説明されても、いい気はしなかった。
「あいつは昔からそうだったな」
思考を現実へと戻した彼は、瞳をすがめた。彼女は足を止め、手をかざしながら大河を見つめていた。陽光を反射する川面は穏やかな秋を感じさせる。腕をむき出しにして上着も羽織っていない彼女の装いは夏そのものだ。しかし季節は移り変わろうとしている。
「おい、リン」
深く息を吸ってから、彼は声を上げた。自分は気を隠していないのだから、ここにいることは彼女も気づいている。そう思い至れば、躊躇う理由などなかった。振り返った彼女が首を傾げるのがわかる。彼は川原に向かって駆け出した。
「何でそんなところで突っ立ってるんだよ。お前、忙しいんじゃなかったのか?」
尋ねる言葉が皮肉混じりになるのは癖のようなものだ。これがよくないのだと自覚はしてるが、もう十年来のことなので直りそうにない。しかし彼女の方は違ったようだ。今までのように唇を尖らせて言い返してくるかと思いきや、困ったように微笑んで髪を耳にかける。
「ああ、バッキオ」
不意に、彼女が別の人間に見えた。わずかな逡巡を見せた黒い双眸は、子どものものではなかった。もうすぐ彼女も十八になるのだという事実に、彼は気がつく。いつの間にか体つきもすっかり女だ。すんなりとした手足の白さが目映い。
「忙しいってのは嘘だったのかよ」
「嘘じゃないわよ。忙しかったんだけど、これからはどうかしらねえ。さすがに長も頼みにくくなるんじゃないかなあ」
言葉を選んで答えてきた彼女の言い様には、引っかかるものがあった。彼は日に焼けて痛んでいる銀の髪もろとも、乱暴にがりがりと頭を掻く。問わないでくれと、彼女の気は訴えているようだった。
気には感情が表れる。技使いでなくとも誰もが持っている空気のようなものだが、それを感じ取ることができるのは技使いだけだ。そしてその事実を、技使いはあまり口にしない。だから普通の人間は何も気にせず暮らしているようだった。技使いのことは、ただ不思議な力が使える便利で羨ましい存在、くらいにしか思っていない。
気が感じられるというのは、世界の見え方が違うのと同義だと言っていたのは、彼女だっただろうか。その真意が、今なら少しはわかる気がする。気は多くの情報をもたらす。
「何が言いたいんだよ。もったいぶるなよ」
いつものように軽口を叩いているつもりでも、そうではないことは彼女に伝わっているのか? この心のさざ波に気づかれているのか? 彼にもそこまではわからない。彼女の気は先ほどと大きく変わらず、わずかな迷いが感じ取れるだけだった。
「もったいぶってるわけじゃないけど」
視線を逸らした彼女の頬へ、風に揺れた黒髪が落ちてくる。背中の中程まで伸ばしていた髪をばっさり切ったのは、夏真っ盛りのことだった。今は軽く肩に触れる程度で、それが何だか見慣れなくて落ち着かない。彼女が何かに変わろうとしているような、そんな心地になる。
「……私、神技隊に選ばれたんだって」
ぽつりと彼女は言った。瞠目した彼は息を呑んだ。その単語が指し示す意味がわからないほど彼も馬鹿ではない。あの宮殿に住む偉そうな『上』が異世界に派遣している技使い。それが神技隊だ。何を目的として招集されているのか、詳細はわかっていない。
異世界にいる化け物を倒すのだとか、犯罪者を捕まえるのだとか、異世界を発展させるために力を尽くすのだとか、変な噂ばかり耳に入っている。確かなのは、異世界に行くということだけだ。未知なる世界に赴くという事実だけ。
「嘘だろ」
それはつまり、彼女がいなくなるということだ。この世界から彼女が消えてしまうということだ。
「断らないのか?」
「神技隊に選ばれて断った人の話、聞いたことある? いないって長は言ってた」
彼女は笑った。ここらでは誰よりも強い技使いとして認識されていた彼女が、頼りにされていた彼女が、羨望と嫉妬の視線を向けられていた彼女が、別人に見えた。諦めるなんて彼女らしくない。おとなしく流れに身を任せるなんて信じられない。
「本気かよ」
「何が?」
「お前、それでいいのかよっ」
どうして自分が怒っているのかも定かではない。荒げた声がむなしく辺りに響く。彼女は不思議そうに小首を傾げ、くすりと笑った。
「何でバッキオが怒ってるの?」
「そ、それは……」
「選ばれちゃったんだからしょうがないでしょ。宮殿には行かなきゃ。それで話を聞いて、それから考える。行くのを拒む理由はないしね。そんなことしても、長が困るでしょう」
怖くないのかとか、皆と離れるのに寂しくないのかとか、尋ねたいことは山ほどあった。しかしそのどれもが喉に張り付いて出てこない。そうしている間に、彼女の気から迷いが消えていった。彼が何も言わずとも彼女は決断したのだ。おそらく、思いを口にすることで。
「私がいなくたってみんなはもう大丈夫。立派な技使いだもの」
「……本当に大丈夫なのかよ」
かろうじて声に出せたのは、そんな一言だった。彼は眉間に皺を寄せる。ぶっきらぼうな言い方になってしまった。彼の言葉は、気ほどには素直に感情を表現してくれない。
「そりゃあ、しばらくは大変かもね? でも慣れるわ。人ってそんなものじゃない? それに神技隊だって、ずっと異世界に住まなきゃいけないってことでもないみたいだし」
「でも戻ってきた奴らは全員宮殿に引きこもってるだろ? つまり、ウィンには戻らないってことだろ」
彼女は故郷であるウィンを捨てるつもりなのか? 憤りにも近い感情が胸の中でくすぶっている。彼女に非があるわけでもないのにおかしな話だ。すると彼女は顔をしかめ、くるりと踵を返した。
「おい」
「バッキオはいつも言いにくいことも口にしちゃうわよね。欠点だけど長所だわ。そうよ、そうなるかもしれない。でもそうならないかもしれない。情報がなーんにもないんだもの、確かなことなんて言えないわ。だから耳障りのいいことだって言えちゃうし、その逆もありよ」
表情と言葉の割に、彼女の気から怒りは感じ取れなかった。そのままゆっくり大河へ近づいていく後ろ姿を、彼は見据える。風にはためく白の長いスカートが下生えを撫でていた。ついで、ほっそりとした腕が川面の方へ伸ばされる。
「小さな子たちのためなら、甘い言葉だけを口にすればいいんでしょうね」
彼女は歌うようにそう続けた。それをよしとはしていない声音だった。
「でも私は事実だけを口にするつもりよ。大丈夫、みんなわかってくれるわ。だからバッキオが誰に何を言っても、私はかまわないわ」
彼女の手が、風を掴む様を想像する。ああ、飛び立つつもりなんだなと彼は悟った。実際に飛ぶわけではない。しかし彼女は飛び立つのだ。いつもそうしているように軽やかに、彼の手を擦り抜けて、逃げていってしまう。ここまでこれるものなら来てみろと笑って、自由に空を駆ける。
彼女を捕まえられたことなど、一度もなかった。
「何だよそれ。オレのこと何だと思ってるんだよ」
彼が悪態を吐くことにも慣れているからだろう、手を下ろした彼女はまた声に出して笑った。「わかってないの?」とでも言いたげな様子だった。わかるわけがない。気は感じ取れるが、全ての感情が読み取れるわけではない。心が読めるわけではない。彼女が自分のことをどう思っているのかは、彼にとっての一番の謎だ。
「バッキオはバッキオでしょ」
聞き慣れた返答に、少なからず落胆するのもいつものこと。その意味を教えて欲しいのだが、彼女は決して口にしない。意地が悪い。
「どう思って欲しいのかを考えずに聞いてくるのは、バッキオの悪い癖だと思うわ。気に頼り過ぎよ」
それでも、今日は普段と少し違った。彼は「え」と声を漏らして瞳を瞬かせる。ちらりとだけ振り返った彼女は、いつになく真顔だった。
「自分の代わりに考えてくれる人なんていないんだから、ちゃんと考えなきゃ。いつか後悔しても知らないわよ」
そう言い残して、彼女は歩き出す。彼に背を向けて踊るように軽やかに、なめらかに、前へと進む。追いかけることを拒絶する後ろ姿だった。
彼女はいつもそうだ。喜怒哀楽がはっきりしていて、短絡的な物言いをしているように見えて、それでいて時に深いところを突いてくる。そして彼を置いてけぼりにする。
「考えろって……」
もう十分に考えている。そう言い返したいのに、声にならなかった。どう思って欲しいのかなどわかりきったことだ。自分という存在を、彼女に認めさせたいだけだ。同じ目の高さで、この広い世界を見たいだけだ。
それなのに一人で勝手に飛び立とうとするなんて……。勝ち逃げなどずるい。許されることではない。
「……くそっ。いつも自分が一番わかってるって顔しやがって。異世界でもどこでも行ってしまえ」
吐き捨てた言葉が弱々しく響いたことに、彼はうんざりとした。今のこの彼の感情は、気としてどう彼女に捉えられているのだろうか?
声は届かなくとも、気は容易く届いてしまう。どれだけ離れていても、よく見知った気なら、探さなくても見つけ出してしまう。これだから困る。
「異世界なら、気も伝わらないだろ」
彼は歯噛みした。本当に、技使いとは難儀な生き物だ。
技使いというのは難儀な生き物だ。
おおよそとはいえ、『気』で相手の感情がわかってしまう。
それを理由に常に気を隠しているような技使いもいるが、そうなると今度は「用心深い人間」として警戒されてしまうから困る。
技使いとは難儀な生き物だ。
宮殿の中というのはひどく息苦しい。そう意識したのは、外の世界を知ってからだった。
もちろん今までにもそういった話は耳にしたことはあったが、しかしあまり実感が伴っていなかった。宮殿の生活に適応している結果なのかもしれない。こんなものかと思えば苦痛には感じなかった。
「はぁ」
そうなると知ってしまった後の方が辛いというもので。ありかは大きなため息を吐いた。図書庫での仕事を終わらせ、後は部屋に戻るだけ。それだけのことなのに体も心も重く感じられる。
白一色で統一された廊下の中を、彼女はとぼとぼと歩いた。技使いが多く住むこの宮殿では、いつも気がひしめいている。人々の思いがたゆたっている。
それだけでも十分重苦しいのに、そこかしこに技が使われているのだ。外があれだけ澄み渡った世界だと、今まで彼女は知らなかった。
「外の人間が宮殿に入ると、酔うというのもわかるわ」
こぼれた独り言が廊下に染み込んでいく。脱力してうなだれると、頬へ髪が落ちてきた。指通りのよいさらりとした黒髪は母譲りで、この長さでは結ぶのも難しい。
だが長く伸ばすのも、短く切り揃えるのも嫌だった。母と似ていると言って比べられてしまう。成長するにつれて、そう言われることが増えてきた。
技使いと一言で括っても、実力差はかなりある。ありかはさほど優秀な方ではない。気の察知には長けているが、それくらいだ。しかも今ではその唯一の拠り所であった長所が、彼女を苦しめている。
「あーりかちゃん!」
と、急に声を掛けられ、彼女の鼓動は跳ねた。近くに気は存在していないはずだった。慌てて顔を上げると、目の前には見知った青年の姿がある。狐色の髪と垂れた目が特徴的な、宮殿でも目立つ存在――ミケルダだ。気を隠していたのだろう。こっそりと仕事を抜け出している彼にはよくあることだった。
「ミ、ミケルダさん」
「久しぶりに顔が見たくなって来ちゃったー」
「そんなことばかり言って、もしかしてまた抜け出してきたんですか?」
「あ、ばれた?」
彼は眉尻を下げながらぺろりと舌を出す。図書庫の辺りは人目にもつきにくいため、上から抜け出してくる際にはよく利用している。真面目な誰かに見つかると、戻ってくださいと怒られるからだ。人懐っこく女好きで陽気な彼だが、これでも『上』の一員なのである。
「ありかちゃん、疲れてるみたいだね。大丈夫? 仕事忙しかった?」
「そういうわけじゃあないんですけど」
彼女はゆるゆると首を横に振った。疲れているのは仕事のせいではない。図書庫の仕事は向いているようで、苦痛を感じたことはなかった。あまり他の人間と関わらなくてすむのも大きい。宮殿に住んでいる人々は皆仕事に追われていて、いつもせかせかと歩いている。余裕がない。彼らの放つ気は、まるでこの宮殿に巣くう呪いのようだ。
「……ミケルダさんは、外にも何度も行ってるんですよね?」
「もちろん。あ、そっか、ありかちゃんはこの間初めて外の仕事行ってきたんだよね?」
「そうなんです」
彼は訳知り顔で相槌を打った。まさかその事実だけで全てを察したというのか? 彼女が首を傾げていると、彼は白い壁にもたれかかる。人目を避けるために羽織っているのか、見慣れない灰色の長衣が揺れた。
「最初はみんなありかちゃんみたいな反応をするよ、誰でも。シイカちゃんもそうだった」
「お母様も?」
優秀な母でもそうだったのかと、彼女は眼を見開いた。何でもそつなくこなし宮殿内の事情にも通じている母――シイカは、ほとんど弱音を吐かない人間だった。昔の苦労話を聞いたことすらない。そんな母の過去を、誰よりも『長生き』な彼は知っているのか。
「ほら、ここはこれだけの気で溢れかえっているでしょ? だから目も曇るんだ。外に出ると、曇りが取れちゃうんだよ。よりはっきり全てが感じ取れるようになっちゃう」
彼は垂れた目を細めた。彼女は探るように辺りへと視線を巡らす。そう、外は澄み切っていた。気を目印に移動することも容易にできる、広い世界だ。次々と悪意の気に晒されるようなことはない。
「世界が晴れたって表現した人もいたなあ。こんな場所だと、気が感じ取れるのもいいことばかりじゃあないんだけどね。ありかちゃんたちみたいに過敏だと余計にね」
肩をすくめた彼から、彼女はまた視線を外す。
自分が過敏である自覚はあった。気に敏いというのは長所でもあり欠点でもある。微細な調整を必要とする技を使う際には大いに役立つ。しかし日常生活においては迷惑なだけだった。他人の負の感情が、絶え間なく突き刺さってくる。これなら曇ったままであった方がましだ。
「……そうですね」
「だからありかちゃんも、たまには息抜きしなよ。ここにこもってると息が詰まるから」
「ミケルダさんは息抜きしすぎだと思いますけどね」
彼女が苦笑すると、彼は頬を掻きながら照れ笑いを浮かべた。仕事をさぼりすぎだと何度も注意されてきた彼は、やはりずっと息苦しさを感じてきたのだろうか? 彼の陽気な笑顔の裏にあるものを思い、彼女は唇を引き結ぶ。
「まあ、でも大丈夫。その感覚の違いにもそのうち慣れるよ。心配しないでありかちゃん」
口の端を上げた彼に、彼女は頷いてみせた。彼が気を隠しているのは、本当にお小言を避けるためだけなのだろうか? 悟られたくない何かがあるのではないか? そう思うと、にわかに胸の奥がざわつく。
技使いとは難儀な生き物だ。
技使いというのは難儀な生き物だ。
特別な力を持っているからと羨ましがられ、ことあるごとに利用される。その一方で、気味が悪いと疎まれる。
それでも他者との繋がりを断ち切ることはできない。孤独には耐えられない。
技使いとは難儀な生き物だ。
「技使いとは難儀な生き物だなあ」
ほうっと吐き出した息と共に、女の口から言葉がこぼれた。それは歌うように朗らかな音色を伴って、夜の空気を揺らす。
「難儀?」
「そう。人々の希望の象徴のように扱われるのに、陰では人外だの化け物だのと罵られる。その差に苦悩する」
問いかける男に対して、女は相槌を打ちながら答えた。夜も更けた頃となれば、鬱蒼とした森の傍を通りかかる者もいない。小道にたたずむのは二人だけだ。今にも消えそうなほどに細い月の下で、女はひらりと手をかざす。
「人間だと言い切ることも許されない。しかし人間であることを止めることもできない。技使いとしか生きられない。難儀な存在だよ」
そうは思わないか、と女は問うた。男は肯定も否定もせずに首を傾ける。夜風がひゅるりと鳴きながら、二人の間を擦り抜けていく。女の長い髪が踊るように揺れた。
「人間である、と思うことを止めたら楽になれるのかもしれないよ。たまにそう声を掛けたくなる」
くすくすと女は笑う。楽しげではあるのに、どこか寂しげだった。いや、哀れんでいるのか。男はため息を吐いて空を仰ぐ。澄み切った深い藍色の空では、月に負けまいと星々が瞬いている。良い夜だ。昼間あんなことがあったとは思えぬ、穏やかな夜だ。
「……そんなこと、思えるはずがないだろう」
男は苦笑した。技使いにとっては技が全てだ。当たり前のように使えるその能力は、確かに普通の人間には持ち得ないもの。
しかしだからといって人であることを止められるわけでもない。空腹をごまかす技はないし、眠らずに過ごすこともできない。愛も欲しい。誰にも頼らず一人で生きていくことは不可能だ。どこまでいっても、技使いは人間だった。
「本当にそうなのかな。そう、思い込んでいるだけかもしれないよ?」
女の悪戯っぽい笑顔はどこか艶めかしい。頼りない月明かりの下で、舞うように一歩前へ踏み出した足が、軽い靴音を立てた。ほっそりとした手が風を撫でる。
「人間でありたいと思っているから、それを否定したくないだけかもしれない」
男には女の言わんとすることがわからない。まるで謎かけだ。一歩一歩確かめるように進む女の後を、男はゆっくり追いかける。
「何かであると認めることも、何かではないと否定することも、あり方には何ら影響はないんだよ」
女は振り返らない。しんと静まりかえった静寂を揺るがすのは、その悠然とした声だけ。世界でただ一人、すべてを知っているかのように見える背中を、月光が照らす。
「何をしたいか、どう生きたいか、どこを目指したいか。何者であるかなど、大切なことには案外影響しない」
そうだろう、と女はまた尋ねた。肩越しに振り向いた横顔には、穏やかな笑みが浮かんでいた。男は頷く。
「そうだな」
何者かであることと、何をなすかは、全く別の話だ。技使いであってもなくても、人間であってもなくても、目指すべき場所があるならば進むしかない。そう女は言いたいのか。
それは達観した者のみが到達できる場所だろう。普通は彷徨い、惑うものだ。
「技使いというのは、技使いであることに囚われやすい。それ以外の道がないと思い込んでいる。本当に難儀な生き物なんだよ」
再び夜風が二人の間を通り抜けていく。そうかもしれない、と男は首を縦に振った。