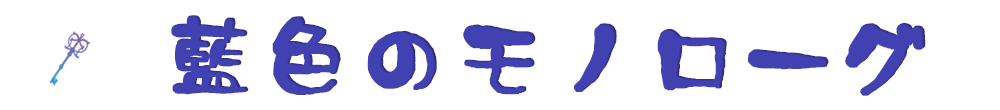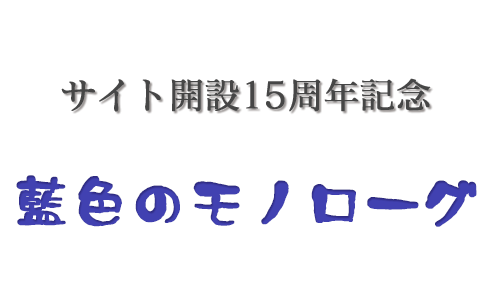大切なものの守り方(ファラールの舞曲より)
「シィラは誰かに料理とか教えてもらったの?」
そろそろ就寝という時刻。ベッドに潜り込もうとしたゼジッテリカは、ふいと湧き上がった疑問をそのままぶつけてみた。
シィラと作ったクッキーは好評で、誰もが美味しいと言ってくれた。いつか自分でも作れるようになるだろうか。自分一人でも、作れるようになるだろうか。様々な不安で胸が押しつぶされそうな心地になる。
きゅっと唇を引き結んだゼジッテリカは、扉を確認するシィラの背を見つめた。
「料理ですか? 習ったことはありませんよ」
振り返ったシィラは不思議そうに首を傾げる。緩く結わえられた髪がふわりとゆれた。
「じゃああのクッキーは?」
「あの? ああ、あれは作り方が書いた本をもらったんです」
にこりと微笑むシィラを、ゼジッテリカはまじまじと見上げた。それでは本を見ただけで作れるようになったというのか。ゼジッテリカにそれが可能となるのは、一体何年後の話だろう。
「読んで簡単に作れるの?」
「そうとも限らないみたいですが。そうですね、お菓子作りは実験と同じだと、教えてもらったんです。そのおかげですかね」
ふふ、と笑ったシィラが誰かを思い出しているのは、ゼジッテリカにもわかった。それが幸福な記憶なのだろうというのも予想できた。じんわり胸が温かくなると同時に、冷たい空気も流れ込んでくる。
懐かしむというのは、終わりがあったからできることだ。ゼジッテリカもいつか、今日のことを思い出すのだろうか。思い出せるのだろうか。
「リカ様も作れますよ。一緒に作れたんですから、大丈夫です。作れます」
まるで言い聞かせるようにシィラはそう繰り返した。自分はいつか今日のことをなぞるように、クッキーを作るのだろうか。ゼジッテリカは考える。その時は一人だろうか。それとも別の誰かと一緒だろうか。
「それじゃあその本、リカ様にお渡ししますね」
すると名案が思いついたとばかりに、シィラは手を打った。思わぬ話にゼジッテリカは眼を見開く。そこまでしてもらうつもりなどなかったのに。
「え、い、いいよ!」
「私が持っているよりもリカ様が持っていた方がきっと本も喜びます。私、一人では作ることありませんから」
シィラはゆるゆると頭を振った。しかしそれはきっと大切な思い出の品に違いなかった。いまだに持ち歩いているくらいなのだから。それをゼジッテリカが奪い取るわけにはいかない。
「でも、大切なものなんでしょう?」
「本は読んでくれる人がいてこそですよ。だからどうか受け取ってください」
小首を傾げるシィラを見ていると、勝てないと直感的に悟った。どんなに言葉を重ねたところで、自分は子どもで相手は大人だ。言い負かされてしまう。だからといって本を突っぱねて叩き落とすような真似もしたくはなかった。――そう思ってしまった時点で、ゼジッテリカの負けなのだ。
「またテキア様に作ってあげてください」
そう告げられ、ゼジッテリカは渋々と頷いた。叔父の名前を出されるのは、やはり弱かった。